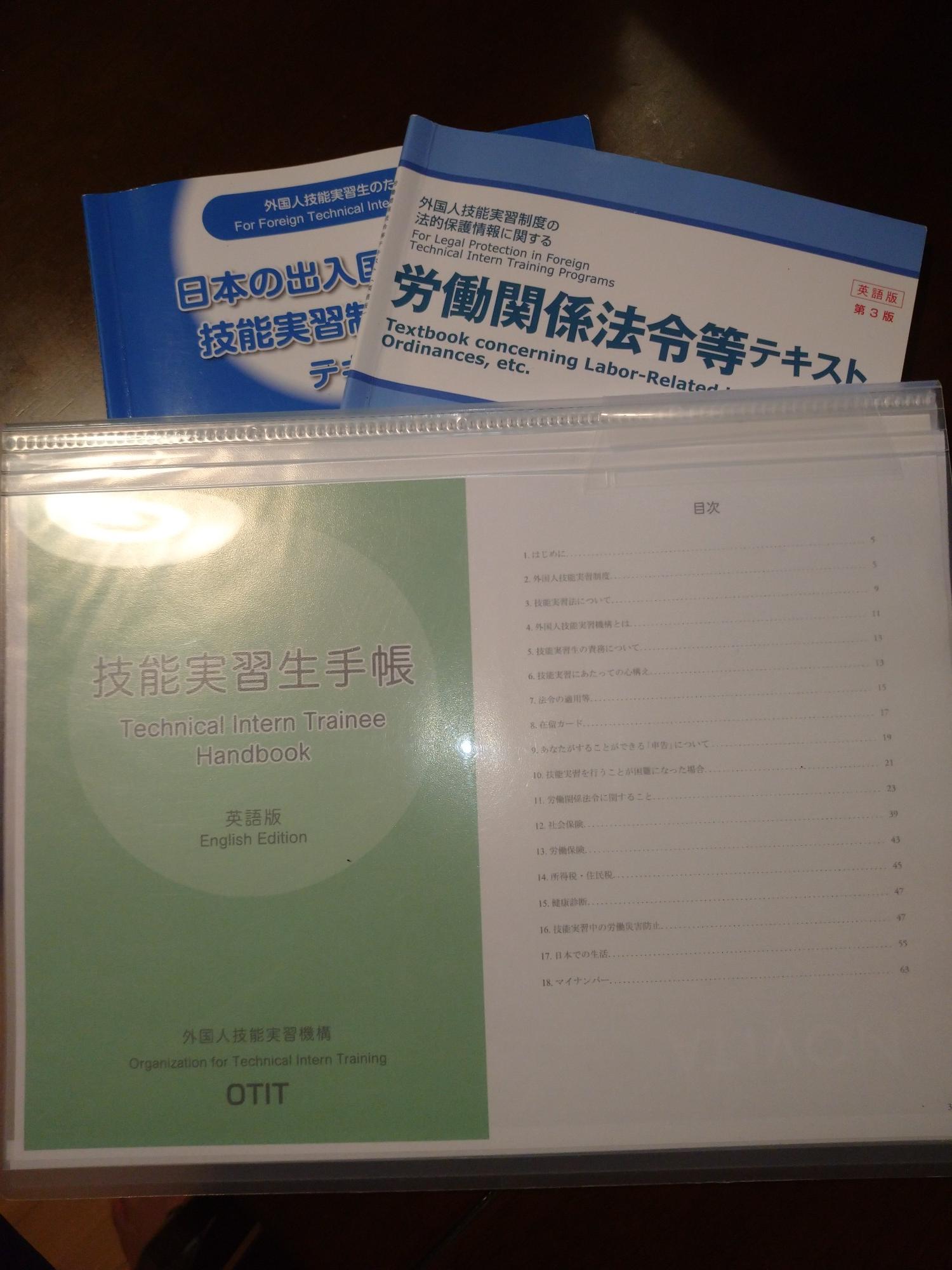高度専門職資格にできて永住権にできないこと(親の帯同、呼び寄せ) (635)
10年程前に「高度専門職」という資格ができました。
これは、ある一定の要件を満たせば、被雇用者でも経営者でもなることができます。
位置付けとしては、就労系ビザ → 高度専門職ビザ → 永住権 となります。
このビザ(資格)を取得すると、永住権ほどではないにしろ
できる仕事の範囲が広がります。
後々永住権の審査を受けるときも、高度専門職ビザ(資格)を持っていると
審査前からの信頼度は違います。
一般的に就労系ビザ(資格)から永住権の申請をし、
審査が終了するのに半年前後かかると言われます。
当事務所で高度専門職ビザ(資格)から永住権申請をしたときには、
その時の入国管理庁の込み具合にもよるでしょうが、
3ヶ月での永住権取得になりました。
この高度専門職ビザにできて永住権にできない事があります。
それは、親(片親)の帯同(呼び寄せ)です。
現在、日本だけでなく多くの国では、本人のビザ(在留資格)による親の帯同は認められていません。
ビザ(在留資格)は本人に与えられているもので、親に与えられたものではないからです。
しかし、この高度専門職ビザはある一定の条件の下で親の帯同を認めています。
高度専門職資格を持つ人が納税や社会保険料をきちっと支払っているか、
親(片親)が一緒に住むことが条件の一つだが、生活費は捻出できるのか、
親の方にも、自国で面倒を見てくれる親族がいる場合は認められない 等等
条件はいろいろあります。
ただ、現在は永住権に親の帯同許可はありません。
高度専門職資格には、一定の条件下ではありますが、
親(片親)の帯同(呼び寄せ)は可能となっています。
永住権を取得する前に高度専門職資格を取得する考え方もあるのかもしれません。
これは、ある一定の要件を満たせば、被雇用者でも経営者でもなることができます。
位置付けとしては、就労系ビザ → 高度専門職ビザ → 永住権 となります。
このビザ(資格)を取得すると、永住権ほどではないにしろ
できる仕事の範囲が広がります。
後々永住権の審査を受けるときも、高度専門職ビザ(資格)を持っていると
審査前からの信頼度は違います。
一般的に就労系ビザ(資格)から永住権の申請をし、
審査が終了するのに半年前後かかると言われます。
当事務所で高度専門職ビザ(資格)から永住権申請をしたときには、
その時の入国管理庁の込み具合にもよるでしょうが、
3ヶ月での永住権取得になりました。
この高度専門職ビザにできて永住権にできない事があります。
それは、親(片親)の帯同(呼び寄せ)です。
現在、日本だけでなく多くの国では、本人のビザ(在留資格)による親の帯同は認められていません。
ビザ(在留資格)は本人に与えられているもので、親に与えられたものではないからです。
しかし、この高度専門職ビザはある一定の条件の下で親の帯同を認めています。
高度専門職資格を持つ人が納税や社会保険料をきちっと支払っているか、
親(片親)が一緒に住むことが条件の一つだが、生活費は捻出できるのか、
親の方にも、自国で面倒を見てくれる親族がいる場合は認められない 等等
条件はいろいろあります。
ただ、現在は永住権に親の帯同許可はありません。
高度専門職資格には、一定の条件下ではありますが、
親(片親)の帯同(呼び寄せ)は可能となっています。
永住権を取得する前に高度専門職資格を取得する考え方もあるのかもしれません。
 BXI Builingual System started translating.
BXI Builingual System started translating.